情報システムのBCP―介護記録・請求業務を止めない対策
介護事業所にとって、利用者の記録や請求業務は事業継続の生命線です。BCPを策定したものの、「本当にこれで大丈夫だろうか」「実際に災害が起きたとき、システムが止まったらどうすればいいのか」と不安を感じている担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、情報システムに焦点を当てたBCP(業務継続計画)の実践的な対策について解説します。クラウドバックアップの導入から紙ベースでの代替手段、さらにシステム復旧の優先順位まで、明日から取り組める具体策をお伝えしていきます。
なぜ情報システムのBCPが重要なのか
近年の介護事業所では、利用者情報の管理から介護記録、請求業務まで、ほぼすべての業務がデジタル化されています。厚生労働省の調査によれば、介護事業所の約70%が何らかの介護ソフトを導入しており、業務効率化に大きく貢献しているのが現状です。
しかし、この便利さは裏を返せば「システムが止まれば業務が止まる」というリスクと表裏一体の関係にあります。2011年の東日本大震災では、多くの事業所でサーバーの物理的な損壊やデータ消失が発生しました。また、2019年の台風19号では、浸水によってサーバールームが水没し、数ヶ月間にわたって請求業務ができなくなった事業所も報告されています。
介護報酬の請求は事業所の収入に直結する重要業務であり、遅延や不能が発生すれば資金繰りに深刻な影響を与えます。さらに、利用者の服薬情報や既往歴などの記録が失われれば、適切なケアの提供そのものが困難になってしまうのです。
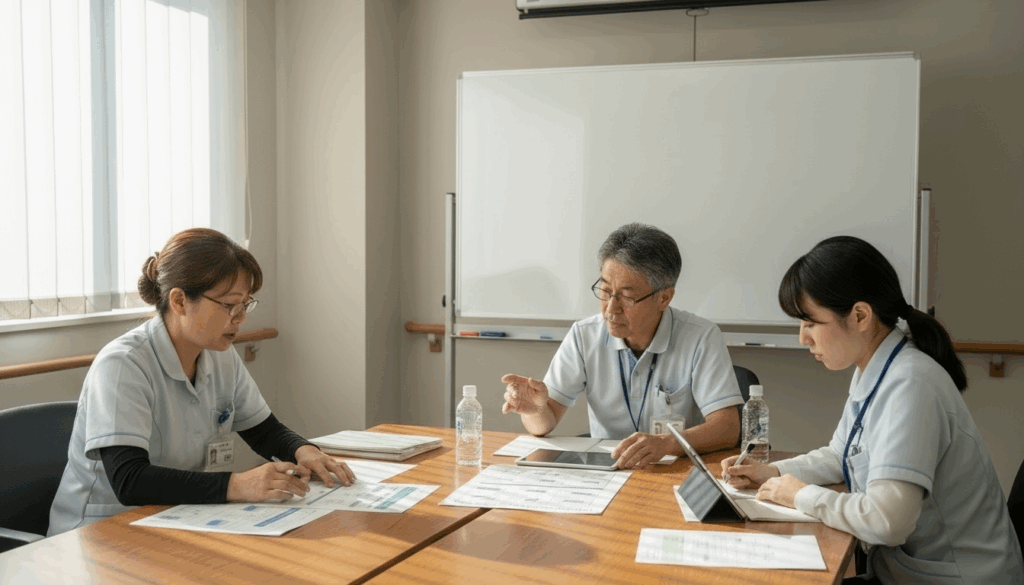
クラウドバックアップ導入の実際
クラウドバックアップとは何か
クラウドバックアップとは、事業所内のサーバーやパソコンに保存されているデータを、インターネット経由で外部のデータセンターに自動的に複製・保管する仕組みを指します。従来の外付けハードディスクやテープによるバックアップと比較して、物理的な災害に強く、遠隔地からでもデータにアクセスできる点が大きな特徴となっています。
導入時に確認すべきポイント
クラウドバックアップを検討する際、まず確認すべきは現在使用している介護ソフトがクラウド対応しているかどうかです。多くの主要な介護ソフトベンダーは、既にクラウド版を提供しているか、クラウドバックアップ機能を実装しています。
導入コストについても現実的な検討が必要でしょう。初期費用として数十万円、月額費用として数万円程度が一般的な相場ですが、事業規模や利用者数によって大きく変動します。ただし、これは「保険」としての投資であり、災害時のデータ復旧費用や業務停止による損失を考えれば、決して高い投資ではありません。
セキュリティ面での懸念を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。確かに個人情報を外部に預けることになりますが、信頼できるクラウド事業者は、介護保険法や個人情報保護法に準拠した厳格なセキュリティ対策を実施しています。具体的には、データの暗号化、アクセス権限の厳密な管理、定期的なセキュリティ監査などが行われているのです。
バックアップ頻度と保存期間の設定
クラウドバックアップを導入しても、適切な設定がなされていなければ意味がありません。介護記録は毎日更新されるため、最低でも1日1回の自動バックアップが必須です。理想的には、営業時間中も数時間おきにバックアップを取得する設定が望ましいでしょう。
保存期間については、介護保険法で定められた記録の保存義務期間である5年間を基準に設定します。ただし、実務的には直近3ヶ月分のデータにすぐアクセスできる状態にしておき、それ以前のデータはアーカイブとして保管する方法が効率的です。

紙ベースでの代替記録方法の準備
なぜ紙の準備が必要なのか
「クラウドバックアップがあれば十分ではないか」と思われるかもしれません。しかし、大規模災害時には停電や通信障害によって、クラウドにもアクセスできない事態が想定されます。実際、2018年の北海道胆振東部地震では、広域停電(ブラックアウト)が発生し、多くの事業所でシステムが使用不能になりました。
このような状況でも、介護サービスは継続しなければなりません。利用者への服薬支援、バイタルチェック、食事・排泄の記録など、記録すべき事項は災害時も変わらないのです。そのため、紙ベースでの代替記録方法を事前に準備しておく必要があります。
実用的な紙フォーマットの作成
紙の代替記録フォームは、通常の電子記録と同じ項目を網羅しつつ、手書きでも迅速に記入できる設計が求められます。具体的には、チェックボックスを多用し、記述欄は最小限に抑えることで、記録時間を短縮できるでしょう。
利用者ごとの個別記録用紙には、氏名、生年月日、要介護度、主な疾患、服薬情報などの基本情報をあらかじめ印刷しておきます。これにより、緊急時でも誰がどのような状態なのか一目で把握可能になります。また、1日の記録を1枚にまとめられるA3サイズの用紙が実務的には使いやすいという声が多く聞かれます。
定期的な訓練の実施
紙の記録フォームを用意しただけでは不十分です。実際に使えるかどうかは、訓練を通じて検証する必要があります。「システムダウンを想定した記録訓練」を実施することで、職員が紙での記録方法に慣れるとともに、フォームの改善点も見えてくるはずです。
訓練では、実際の業務時間中に1時間程度、すべての記録を紙で行ってみます。その際、記録にかかった時間、記入ミスの有無、フォームの使いやすさなどを評価し、次回の改善につなげていくのです。こうした地道な取り組みが、いざという時の対応力を高めることになります。

システム復旧の優先順位を明確にする
復旧優先度の考え方
災害からの復旧段階では、すべてのシステムを同時に復旧させることは困難です。限られたリソース(人員、時間、予算)の中で、どの業務システムから復旧させるべきか、明確な優先順位をつけておく必要があります。
介護事業所における優先順位の基本的な考え方は、「利用者の生命・健康に直結する業務」を最優先とし、次に「事業継続に不可欠な業務」、最後に「その他の業務」という三段階で整理します。
最優先システム:利用者情報と服薬管理
第一優先として復旧すべきは、利用者の基本情報と服薬管理システムになります。利用者の既往歴、アレルギー情報、現在服用中の薬剤などの情報がなければ、適切なケアや医療連携が困難になってしまうからです。
これらの情報は、可能であればクラウドから即座にアクセスできる状態が理想的ですが、通信障害時に備えて、最低限の情報を記載した「緊急時カード」を紙で用意しておくことも有効な対策となります。
第二優先:介護記録システム
次に復旧を目指すのが、日々の介護記録を入力・管理するシステムです。災害発生後、紙での記録が一定期間続いた後、これらをシステムに入力し直す必要が生じます。
記録の遡及入力は膨大な作業量になるため、システムの早期復旧が業務負担の軽減につながります。ただし、遡及入力は通常業務と並行して行うことになるため、職員の負担を考慮しながら段階的に進めることが重要です。
第三優先:請求業務システム
請求業務は事業所の収入に直結する重要な業務ですが、国保連への請求期限には一定の猶予があります。厚生労働省は大規模災害時に請求期限の延長措置を講じることが多く、実際に東日本大震災や熊本地震の際にも特例措置が実施されました。
したがって、請求業務システムの復旧は、利用者ケアに関わるシステムが安定稼働した後に着手すれば良いと言えます。ただし、資金繰りへの影響を最小限に抑えるため、復旧目標時期は明確に設定しておくべきでしょう。
ベンダーとの連携体制の構築
情報システムのBCPにおいて見落とされがちなのが、介護ソフトのベンダーとの連携体制です。災害時、自施設だけでなくベンダー側も被災している可能性があります。
事前にベンダーのBCP対応について確認し、緊急時の連絡体制、復旧支援の内容、代替手段の提供可否などを明確にしておくことが欠かせません。契約書にBCPに関する条項が含まれているか、サービスレベル契約(SLA)で復旧時間が明記されているかなども確認ポイントとなります。
また、ベンダーの担当者が被災して連絡がつかない事態に備え、複数の連絡ルートを確保しておくことも重要です。本社の緊急連絡先、24時間対応のサポートデスク、営業担当者の携帯電話など、複数の連絡手段を記録し、定期的に更新しておきましょう。
定期的な見直しと改善のサイクル
BCPは一度作成したら終わりではありません。システム環境の変化、法改正、新たなリスクの出現などに応じて、継続的に見直していく必要があります。
最低でも年に一度は、情報システムのBCPに関する見直し会議を開催し、バックアップの動作確認、復旧手順の検証、職員の理解度確認などを実施します。その際、前年度の訓練で見つかった課題や改善点を必ず反映させることが、BCPの実効性を高めることにつながるのです。
より実践的なBCP構築に向けて
本記事では、情報システムのBCPにおける基本的な対策について解説してきました。しかし、それぞれの事業所には固有の事情や課題があり、一律の対策では対応しきれない部分も存在します。
介護BCP教育研究所の「介護BCP実践アカデミー」では、情報システムのBCPをはじめとする実践的なノウハウを、事例研究やワークショップを通じて学ぶことができます。自施設の状況に合わせたBCP策定支援や、実地での訓練サポートなど、より具体的な取り組みをご希望の方は、ぜひ専門的な学びの場をご活用ください。
災害は必ず来るものと考え、今できる対策を一つずつ積み重ねていくこと。それが、利用者と職員、そして事業所そのものを守ることにつながります。情報システムのBCPは、決して難しいものではありません。一歩ずつ、確実に進めていきましょう。


