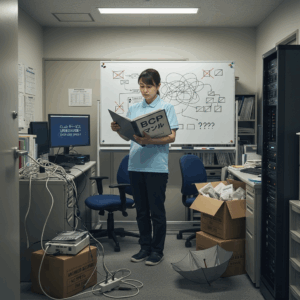【災害時の利用者安全確保】マニュアルBCPとの違い・サービス別対応のポイント
介護事業所において、利用者の安全確保は最優先事項です。しかし、業務継続計画(BCP)を策定したものの、「実際の災害時に何をすればよいのか」「マニュアルとBCPの使い分けがわからない」という声を多くお聞きします。本記事では、BCPと災害時対応マニュアルの違いを明確にし、各介護サービスにおける安全確保のポイントを詳しく解説します。
BCPと災害時対応マニュアルの根本的な違い
BCPの本質と役割
業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)は、災害や緊急事態が発生した際に事業を継続するための戦略的な計画書です。BCPの主な目的は、「どのような状況下でも利用者への介護サービスを可能な限り継続する」ことにあります。
具体的には、被災後の復旧目標時間の設定、優先業務の選定、代替サービスや拠点の確保、職員の参集計画、関係機関との連携体制などの大枠を定めています。BCPは言わば「サービス継続のための設計図」であり、長期的視点から組織全体の対応方針を示すものです。
災害時対応マニュアルの特徴
一方、災害時対応マニュアルは、実際に災害が発生した瞬間から初動対応までの具体的な行動手順を詳細に記載したものです。「誰が」「いつ」「何を」「どのように」行うかを明確に示し、現場の職員が迷わずに行動できることを目的としています。
例えば、地震発生時の初動対応では「揺れを感じたら即座に利用者の安全確保を最優先とし、テーブルの下や壁際から離れた安全な場所への誘導を開始する」といった具体的な行動が記載されます。マニュアルは「その場での実行手順書」と考えるとよいでしょう。
両者の連携と補完関係
BCPとマニュアルは対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。BCPで定めた基本方針に基づき、マニュアルで具体的な行動手順を詳細化することで、理論と実践の橋渡しが可能になります。
重要なのは、BCPの内容とマニュアルの手順に矛盾がないよう、定期的に両方を見直し、整合性を保つことです。また、職員研修においても、BCP教育とマニュアル訓練の両方を実施し、理解の定着を図る必要があります。
介護サービス別の安全確保ポイント
特別養護老人ホーム(特養)における安全確保
特別養護老人ホームは24時間体制で要介護度の高い利用者を受け入れているため、災害時の安全確保には特に綿密な準備が必要です。
夜間帯の対応では、少ない職員数で多くの利用者の安全を確保しなければなりません。そのため、居室から共用スペースへの避難経路を複数確保し、車椅子や寝たきりの利用者の移動方法を事前に検討しておくことが重要です。また、人工呼吸器や酸素濃縮器などの医療機器を使用している利用者については、停電時の代替電源確保と移動時の安全性を両立させる計画が不可欠です。
食事の継続提供も重要な課題です。調理設備が使用できない場合を想定し、備蓄食品の種類と量、調理方法の代替案を用意しておく必要があります。特に、嚥下機能に問題のある利用者向けの食事形態を維持するための準備は、生命に直結する重要事項です。
介護老人保健施設における医療機能の維持

介護老人保健施設(老健)は、病院と家庭の中間的な役割を担う施設として、医療と介護の両面での対応が求められます。災害時においても、この医療機能を可能な限り維持することが利用者の安全確保に直結します。
老健には医師が常勤しており、看護師も24時間配置されているため、災害時の医療対応においては地域の中核的な役割を担うことが期待されます。そのため、施設内の医療設備(酸素供給装置、人工呼吸器、透析装置など)の災害時対応計画を詳細に策定し、停電時の代替電源確保や機器の移動方法を明確にしておく必要があります。
薬剤管理においては、老健では多種多様な医薬品を常備しているため、災害時の薬剤保管と供給継続が重要な課題となります。冷蔵保存が必要な薬剤については、停電時の温度管理方法を確立し、必要に応じて近隣の医療機関への一時的な移管も検討しておく必要があります。
リハビリテーション機能の継続も老健の重要な特徴です。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職による機能訓練は、利用者の身体機能維持に不可欠です。災害により訓練設備が使用できなくなった場合でも、代替的な訓練方法を実施できるよう、事前の準備と職員の訓練が必要です。
また、老健は在宅復帰を目指す利用者が多いため、災害により家屋が被害を受けた利用者については、退所計画の見直しや長期入所への変更など、柔軟な対応が求められます。そのため、行政機関や地域包括支援センターとの密接な連携体制を構築しておくことが重要です。
デイサービスセンターの特殊事情への対応
デイサービスは日中のみの営業であるため、災害発生時の状況によって対応が大きく変わります。
営業時間中に災害が発生した場合、利用者の家族への連絡と迎えの依頼が最優先となります。しかし、交通機関の麻痺や道路の寸断により、家族がすぐに迎えに来られない可能性もあります。このような状況を想定し、一時的に利用者を施設で保護するための備蓄品(食料、毛布、医薬品など)を準備しておくことが重要です。
また、デイサービス利用者の多くは自宅での生活を続けているため、災害後の安否確認体制も重要な要素です。電話回線の不通に備え、職員による直接訪問での安否確認ルートを事前に策定しておく必要があります。
訪問介護における分散型リスクへの対策

訪問介護は利用者の自宅でサービスを提供するため、災害時のリスクが地理的に分散している特徴があります。
各利用者宅の立地条件(洪水想定区域、土砂災害警戒区域など)を事前に把握し、災害種別に応じた訪問の可否判断基準を明確にしておくことが重要です。また、道路の寸断により通常ルートでの訪問が困難になることを想定し、代替ルートの確認や近隣事業所との連携体制を構築しておく必要があります。
ヘルパーの安全確保も重要な課題です。災害発生時の無理な訪問は二次災害のリスクを高めるため、気象警報発令時の訪問中止基準や、ヘルパーから事業所への安否報告体制を明確にしておくことが必要です。
通所リハビリ(デイケア)における医療連携の強化
通所介護施設では、リハビリテーションや医療的ケアを必要とする利用者が多いため、災害時の医療連携体制の確保が特に重要です。
主治医や協力医療機関との災害時連絡体制を確立し、利用者の医療情報を迅速に共有できる仕組みを整備しておく必要があります。また、服薬管理についても、災害により薬局からの薬剤調達が困難になることを想定し、緊急時の代替調達ルートを確保しておくことが重要です。
理学療法士や作業療法士などの専門職との連携も重要な要素です。災害により施設の設備が使用できなくなった場合でも、利用者の身体機能維持のための代替プログラムを実施できるよう、事前の準備と訓練が必要です。
居宅介護支援における情報管理と連絡調整機能
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)は、直接介護サービスを提供する施設ではありませんが、災害時には利用者と各種サービス事業所を結ぶ重要なハブ機能を担います。
ケアマネジャーの最重要任務は、担当利用者の安否確認と情報の一元管理です。災害発生後、可能な限り早期に全担当利用者の安否確認を行い、その情報を地域包括支援センターや行政機関に報告する体制を整備しておく必要があります。また、利用者の身体状況、服薬情報、緊急連絡先、利用サービス事業所などの情報を災害時でも確認できるよう、複数の手段でデータを保管しておくことが重要です。
さらに、災害により通常利用している介護サービス事業所が利用できなくなった場合、代替サービスの調整が必要になります。そのため、地域内の介護サービス事業所の被災状況を把握し、利用者のニーズに応じた代替サービスを迅速に手配できるよう、平時から他事業所との関係構築に努めることが重要です。
グループホームにおける認知症ケアの継続
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)では、認知症の利用者が住み慣れた環境で生活しているため、災害時の環境変化による混乱を最小限に抑えることが重要な課題となります。
認知症の方は環境の変化に敏感で、災害という非常事態により不安や混乱が増大する可能性があります。そのため、避難が必要な場合でも、できる限り普段使用している物品(写真、お気に入りの品物など)を持参し、心理的安定を図ることが重要です。また、職員が利用者の個別の特性や対応方法を熟知していることが、災害時の適切なケア継続につながります。
医療面では、認知症の進行抑制薬や精神症状に対する薬剤の継続的な服薬が重要です。災害により医療機関や薬局からの薬剤調達が困難になることを想定し、最低限7日分程度の予備薬を確保しておくことが必要です。また、利用者の医療情報や服薬情報を災害時でも確認できるよう、紙ベースでの情報管理も並行して行っておくことが重要です。
夜間対応についても特別な配慮が必要です。グループホームは夜間の職員配置が少ないため、近隣住民や他のグループホームとの相互支援体制を構築し、緊急時の応援要請ができる仕組みを整備しておくことが重要です。
災害種別に応じた対応の違い
地震災害への対応
地震は予知が困難で突発的に発生するため、初動対応の迅速性が利用者の安全を左右します。
建物の安全性確認は最重要項目です。地震発生後は、建物の構造的損傷がないかを専門的知識を持つ職員が確認し、安全性に疑問がある場合は速やかに避難を開始する必要があります。また、エレベーターの使用停止、ガスの元栓閉鎖、電気設備の点検など、二次災害防止のための確認事項を事前にチェックリスト化しておくことが重要です。
水害・台風への対応
水害や台風は気象予報により事前の準備時間が確保できるため、予防的な対応が可能です。
避難準備情報や避難勧告の発令段階に応じた行動計画を策定し、利用者の避難完了までに要する時間を考慮した早期の判断が必要です。特に、車椅子利用者や寝たきりの利用者の避難には時間がかかるため、気象情報を注視し、余裕をもった避難開始を心がける必要があります。
職員の安全確保と参集体制
職員の安全を最優先とする考え方
利用者の安全確保のためには、まず職員自身の安全が確保されていることが前提となります。
職員が被災により出勤できない状況や、家族の安否が不明な状況では、適切な介護サービスの提供は困難です。そのため、職員の居住地域の災害リスク把握、緊急時の連絡体制確立、家族の安否確認方法の周知などを通じて、職員が安心して業務に従事できる環境を整備することが重要です。
段階的参集計画の策定
災害の規模や種類に応じて、職員の参集計画を段階的に設定することが効果的です。
初動対応に必要な最小限の職員数から、通常業務レベルに必要な職員数まで、段階的な参集計画を策定しておくことで、無理のない業務継続が可能になります。また、職員の居住地と施設までの距離、交通手段、家族構成などを考慮し、参集の優先順位を事前に決めておくことも重要です。
地域連携の重要性
行政機関との連携体制
災害時の介護事業所の対応は、単独では限界があります。市町村の災害対策本部や地域包括支援センターとの連携体制を構築し、災害時の情報共有や支援体制を確立しておくことが重要です。
特に、避難所における要配慮者支援や、他の介護事業所との利用者の相互受け入れについては、平時からの調整と訓練が必要です。また、災害時における介護報酬の取り扱いや手続きの簡素化についても、行政機関との事前調整が重要になります。
同業他社との相互支援体制
同一地域内の介護事業所同士での相互支援体制の構築も重要な要素です。
災害により自施設での業務継続が困難になった場合に、近隣の介護事業所で利用者を一時的に受け入れてもらえる体制があれば、利用者の安全確保と家族の安心につながります。このような相互支援体制は、業界団体や地域の介護事業所連絡会などを通じて構築することが効果的です。
訓練と改善の継続
実効性のある訓練の実施
BCPや災害時対応マニュアルは、策定しただけでは意味がありません。定期的な訓練を通じて職員の理解を深め、実際の災害時に適切に行動できるよう準備することが重要です。
訓練は、机上での想定訓練から実際の避難訓練まで、段階的に実施することが効果的です。また、夜間や悪天候など、様々な状況を想定した訓練を実施することで、より実践的な対応力を身につけることができます。
継続的な見直しと改善
災害対応計画は一度策定すれば完成というものではありません。訓練での課題発見、法制度の変更、施設の改修、職員の入れ替わりなどに応じて、継続的に見直しと改善を行う必要があります。
また、実際に災害を経験した他の介護事業所の事例や教訓を積極的に収集し、自施設の計画に反映させることも重要です。災害対応は経験から学ぶことが多いため、他施設の経験を自施設の改善に活かす姿勢が大切です。
まとめ
災害時の利用者安全確保は、BCPという戦略的計画と具体的な行動マニュアルの両輪により実現されます。BCPで示した基本方針を、サービス種別の特性に応じた具体的な手順に落とし込み、継続的な訓練と改善を通じて実効性を高めていくことが重要です。
介護事業所の皆様には、利用者の生命と安全を守るという重要な責任があります。そのためには、平時からの十分な準備と、職員一人ひとりの意識向上が不可欠です。
災害はいつ発生するかわかりません。今日からでも、自施設の災害対応体制を見直し、改善に取り組んでいただきたいと思います。介護BCP教育研究所では、皆様の取り組みを支援するための無料セミナーを定期的に開催しております。より詳しい内容については、ぜひセミナーにご参加いただき、具体的な改善策を一緒に検討させていただければと思います。