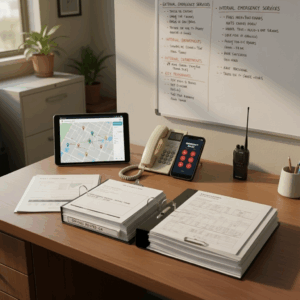BCP訓練の企画・実施方法―形だけにならない効果的な訓練とは
厚生労働省のひな形を使ってBCP(業務継続計画)を作成したものの、「これで本当に大丈夫なのだろうか」「次に何をすればいいのか」と悩んでいる介護施設・事業所のBCP担当者の方は少なくありません。BCPは作成して終わりではなく、訓練を通じて検証し、改善を重ねることで初めて実効性のあるものになります。今回は、施設系サービスでは年2回、在宅系サービスでは年1回義務付けられているBCP訓練を形骸化させず、施設の災害対応力を確実に高めるための具体的な方法をご紹介します。
BCPを「使える計画」にするための訓練の位置づけ
多くの施設・事業所では、義務だから訓練を実施するという受け身の姿勢になりがちです。しかし、訓練の本質は「作成したBCPが実際に機能するかを確認し、改善点を見つける機会」にあります。介護現場では、災害時でも利用者の命と尊厳を守り続けなければなりません。そのためには、計画書に書かれた手順が現場の実態に即しているか、職員が実際に行動できるかを検証することが不可欠です。
訓練を通じて発見される課題は、計画の弱点を教えてくれる貴重な情報です。「この手順では時間がかかりすぎる」「備蓄品の保管場所を職員が知らない」「夜勤帯では人手が足りない」といった現実的な問題は、机上では見えてきません。訓練は、こうした問題を安全な環境で発見し、改善する絶好の機会なのです。

施設系サービス:年2回の訓練を最大限活用する戦略的アプローチ
施設系サービスでは年2回の訓練機会があります。この限られた機会を有効活用するには、それぞれの訓練に明確な目的を持たせ、段階的にレベルアップしていく設計が重要です。
1回目の訓練では、BCPの基本的な流れと職員の役割分担を確認することに重点を置きます。例えば、地震発生直後の安全確認、利用者の安否確認手順、初動対応における各チームの動きなど、基礎的な部分を全職員が理解することを目標にします。この段階では、完璧な実施よりも「やってみること」が大切です。初めての訓練では、混乱や戸惑いが生じるのは当然です。むしろ、どこで混乱したか、何が分かりにくかったかを記録することが次につながります。
2回目の訓練では、1回目の反省を踏まえ、より実践的なシナリオに挑戦します。例えば、夜間帯や週末など職員が手薄な時間帯を想定したり、複数の問題が同時発生する状況を設定したりします。また、1回目で明らかになった課題への対応策が機能するかを検証する場としても活用できます。このように、2回の訓練を連続したPDCAサイクルの一部として位置づけることで、着実な改善が図れます。
さらに、毎年同じ内容を繰り返すのではなく、年度ごとにテーマを設定することも効果的です。今年度は地震対策、来年度は水害対策、その次は感染症対策といったように、優先度の高いリスクから順に訓練することで、数年かけて総合的な対応力を構築していけます。
在宅系サービス:年1回の訓練を充実させる工夫
在宅系サービスでは年1回の訓練となりますので、より計画的な準備が求められます。1回の訓練で全てを網羅することは困難ですから、何を優先的に確認するかの判断が重要になります。
在宅系サービスの特性として、利用者が広範囲に分散していること、発災時に職員も被災者となる可能性が高いこと、通信手段が途絶えた場合の安否確認が困難であることなどが挙げられます。こうした特性を踏まえ、例えば「発災後24時間以内の利用者安否確認」や「職員の参集可能性の把握」「代替手段による連絡体制の確認」など、在宅系ならではの重要ポイントに絞って訓練を行うことが効果的です。
また、年1回という制約があるからこそ、訓練前の事前学習や訓練後の振り返りをより丁寧に行うことで、訓練効果を最大化できます。例えば、訓練の1ヶ月前からBCPの内容を職員に周知し、各自の役割を再確認してもらう時間を設けることで、当日の訓練がより実りあるものになります。

効果的なシナリオ作成の実践的ポイント
訓練シナリオの質が、訓練の効果を大きく左右します。ここでは、介護施設・事業所特有の状況を踏まえた実践的なシナリオ作成のポイントをお伝えします。
まず重要なのは、自施設・事業所の実態に合わせたリアルなシナリオを作ることです。厚労省のひな形は汎用性を重視しているため、そのまま使うと抽象的で現場感に欠ける訓練になりがちです。例えば、「地震が発生しました」という設定だけでなく、「震度6強の地震が午前3時に発生。夜勤職員は3名のみ。停電により照明と空調が停止し、エレベーターも使用不可。一部の利用者から『怖い』という声が上がり始めている」というように、具体的な状況を設定します。このレベルの詳細さがあると、職員は「自分だったらどう動くか」をイメージしやすくなります。
次に、段階的な情報提供を組み込むことです。実際の災害では、状況が時間とともに変化し、新たな情報が入ってきます。訓練でも同様に、「発災直後」「30分後に〇〇の情報が入る」「1時間後に△△の事態が発生」というように、時系列で情報を小出しにしていきます。これにより、刻々と変化する状況に応じた判断力や対応の柔軟性を養うことができます。
また、シナリオには必ず「困難な要素」を盛り込みましょう。全てが計画通りに進む訓練では、現実の災害対応力は身につきません。例えば、「施設長が不在」「備蓄倉庫の鍵が見つからない」「想定していた避難経路が使えない」「家族からの問い合わせ電話が殺到」といった想定外の事態を意図的に設定します。こうした困難にぶつかることで、代替手段を考える力や臨機応変な対応力が鍛えられます。
施設系と在宅系では、シナリオの重点も変わってきます。施設系では「施設内での利用者の安全確保」「限られた職員での対応」「ライフライン停止時の継続的ケア」などが中心となります。一方、在宅系では「広範囲に分散した利用者の安否確認」「職員自身の被災状況の把握」「訪問経路の寸断」「優先順位の判断」などに焦点を当てたシナリオが効果的です。
訓練結果を計画に確実にフィードバックする方法
訓練を実施して満足してしまい、そこで終わってしまうケースが非常に多く見られます。しかし、訓練の真の価値は、そこで得られた気づきをBCPに反映させることにあります。効果的なフィードバックのプロセスをご紹介します。
訓練直後には必ず振り返りの時間を設けましょう。記憶が新鮮なうちに、参加者全員で気づいた点を共有します。この際、「良かった点」と「改善が必要な点」の両方を挙げることが重要です。良かった点を確認することで、職員の自信につながり、改善点を指摘することで具体的な課題が明確になります。振り返りでは、役職や経験年数に関わらず、全ての参加者が意見を言える雰囲気づくりが大切です。新人職員や非常勤職員の視点こそ、ベテランが見落としがちな問題を発見できることがあります。
振り返りで出た意見は、必ず文書化します。口頭での共有だけでは、時間とともに忘れられてしまいます。訓練報告書として、「訓練の概要」「参加者」「シナリオ」「実施内容」「良かった点」「課題」「改善策」をまとめます。この報告書は、次回の訓練計画や年度末のBCP見直しの際に貴重な資料となります。
重要なのは、発見された課題に優先順位をつけることです。全ての課題を一度に解決しようとすると、かえって何も進まなくなります。「すぐに対応できること」「時間をかけて取り組むこと」「予算が必要なこと」というように分類し、できることから着実に改善していきます。例えば、「備蓄品リストを見やすく更新する」「緊急連絡網の様式を変更する」といったことはすぐに実行できます。一方、「非常用電源の増設」「備蓄品の追加購入」などは予算措置が必要ですから、次年度の事業計画に盛り込むことになります。
BCPの更新は、訓練後できるだけ早い時期に行うことが理想です。訓練から時間が経つと、担当者の異動や記憶の薄れにより、せっかくの気づきが活かされなくなります。訓練実施後1ヶ月以内を目処に、必要な修正をBCPに反映させましょう。修正箇所は赤字で示すなど、何がどう変わったかが分かるようにしておくと、次回の訓練時に「前回の改善点が機能しているか」を確認できます。
さらに、訓練結果は全職員に共有することが重要です。訓練に参加できなかった職員にも、どんな訓練が行われ、何が課題として見つかり、どう改善されたかを伝えることで、組織全体のBCP意識が高まります。回覧や職員会議での報告、写真や動画を活用した共有など、自施設・事業所に合った方法で情報を広げていきましょう。
継続的改善のサイクルを回し続けるために
BCP訓練は、一度やれば終わりというものではありません。毎年の訓練を通じて、少しずつ精度を高め、職員の対応力を向上させていくプロセスです。完璧を目指す必要はありません。むしろ、「今年はこれができるようになった」という小さな前進を積み重ねることが大切です。
初めてのBCP訓練では、不安や戸惑いがあって当然です。厚労省のひな形で作ったBCPが自施設・事業所に本当に合っているのか、訓練のやり方が正しいのか、疑問を感じることもあるでしょう。しかし、完璧な計画や訓練は存在しません。大切なのは、やってみること、そして気づいたことを改善していくことです。
今回ご紹介した方法を参考に、まずは次の訓練に向けて一歩を踏み出してみてください。訓練を重ねるごとに、職員の意識が変わり、対応がスムーズになり、計画の実効性が高まっていくことを実感できるはずです。利用者の安全と安心を守るため、そして職員自身を守るため、実効性のあるBCPを育てていきましょう。