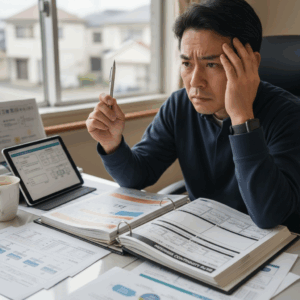小規模事業所が直面しやすいBCP策定の落とし穴
「とりあえず形だけ作ったBCP」では、災害時に全く機能しません。特に小規模事業所は、人的・時間的制約から陥りやすい失敗があります。本記事では、その典型例と回避策を紹介します。
はじめに:形式的なBCPの危険性
介護事業所において業務継続計画(BCP)の策定が義務化されて以降、多くの小規模事業所が厚生労働省のひな形を活用してBCPを作成しています。しかし、「とりあえず作った」BCPと「実際に機能する」BCPには大きな差があります。
災害や感染症の拡大といった緊急事態が発生した際、形式的なBCPしか持たない事業所では、職員は何をすべきかわからず、利用者の安全確保や継続的なサービス提供に支障をきたす恐れがあります。特に職員数が限られている小規模事業所では、この問題がより深刻になりがちです。
では、なぜ多くの小規模事業所が実効性のあるBCPを策定できずにいるのでしょうか。その主な原因と、それを回避するための具体的な方法について詳しく見ていきましょう。
1. テンプレートの丸写しで失敗する理由
ひな形に頼りすぎる危険性
厚生労働省が提供するBCPひな形は、確かに優れた指針となります。しかし、多くの小規模事業所が犯しがちな最大の間違いは、このひな形をそのまま事業所名だけ変更してBCPとして完成させてしまうことです。
ひな形は、あくまで「標準的な事業所」を想定して作られています。しかし実際の介護事業所は、それぞれ異なる特徴を持っています。たとえば、建物の構造、立地条件、職員の年齢構成、利用者の介護度、近隣の医療機関との関係など、すべて異なる条件下で運営されています。
具体例で見る「丸写し」の問題点
例えば、ひな形では「近隣の協力医療機関との連携」について記載されていますが、これをそのまま採用した事業所で実際に問題が発生したケースがあります。その事業所の近隣には確かに病院がありましたが、災害時の受け入れ体制について具体的な取り決めがなく、いざという時に連携が取れませんでした。
また、「職員の安否確認手順」についても、ひな形では電話連絡を基本としていましたが、実際の災害時には通信網が麻痺することが多く、SNSや災害用伝言板など複数の連絡手段を事前に確認していなかった事業所では、職員の安否確認に数日を要した例もあります。
自施設の実情に合わせることの重要性
BCPを実効性のあるものにするためには、ひな形を参考にしながらも、自施設の実情を詳細に分析し、それに基づいた内容に修正する必要があります。これは単に文言を変更するレベルではなく、施設の立地条件、建物の構造、職員体制、利用者の特性、地域の特徴などを総合的に考慮した上で、実際の行動計画を策定することを意味します。
たとえば、河川の近くに位置する事業所であれば水害対策により重点を置く必要がありますし、高齢化が進んだ地域にある事業所では、災害時に協力を得られる近隣住民が限られることを前提とした計画が必要になります。
2. 現場に即していないBCPのリスク
職員が覚えられない複雑な手順
現場に即していないBCPの典型的な問題として、手順が複雑すぎることが挙げられます。ひな形をそのまま使用した場合、様々なケースに対応するため非常に詳細で複雑な手順が記載されていることがありますが、これを職員全員が覚えて実践することは現実的ではありません。
特に小規模事業所では、職員一人ひとりが複数の役割を担うことが一般的です。災害時という極めてストレスの高い状況下で、普段から慣れ親しんでいない複雑な手順を正確に実行することは困難を極めます。
実際の業務フローとの乖離
また、BCPの手順が日常業務の流れと大きく異なっている場合も問題となります。普段とは全く違う動き方を求められると、緊急時に混乱を招く原因となります。効果的なBCPは、可能な限り日常業務の延長線上で実行できるよう設計されるべきです。
例えば、普段は看護師が利用者の健康チェックを最初に行う施設で、BCPでは介護職員が最初に安否確認を行うとなっていた場合、災害時に「誰が最初に何をするか」で混乱が生じる可能性があります。
定期的な見直しがされない問題
現場に即していないBCPのもう一つの大きな問題は、作成後の見直しが適切に行われないことです。職員の入れ替わり、利用者の状況変化、近隣環境の変化など、事業所を取り巻く環境は常に変化しています。しかし、現場の実情を反映していないBCPは、これらの変化に対応した更新が行われにくく、時間の経過とともに実態との乖離がさらに大きくなってしまいます。
訓練時に発覚する問題点
実際に避難訓練や机上訓練を行うと、BCPの問題点が浮き彫りになることがあります。しかし、ひな形をそのまま使用している事業所では、「BCPに書いてある通りにできない」という事態が発生しても、「訓練のやり方が悪い」と考えてしまい、BCP自体の見直しに至らないケースが少なくありません。
訓練は BCPの有効性を検証し、改善点を見つけるための重要な機会です。訓練で浮上した問題は、BCP改善のための貴重な情報として活用すべきなのです。

3. 成功する小規模事業所の工夫
シンプルで覚えやすい手順の作成
成功している小規模事業所のBCPには共通した特徴があります。まず、手順がシンプルで覚えやすいことです。これらの事業所では、「誰でも、いつでも、迷わずに実行できる」ことを重視し、複雑な判断を要する部分を可能な限り排除しています。
例えば、ある小規模デイサービスでは、災害発生時の初動対応を「まず利用者の安全確保、次に安否確認、最後に家族連絡」という3段階に単純化しました。それぞれの段階で具体的に何をするかは、職員の経験レベルに応じて詳細度を調整し、新人職員でも迷わずに行動できるよう配慮されています。
職員の役割分担の明確化
小規模事業所では職員数が限られているため、一人ひとりの役割が非常に重要になります。成功している事業所では、平時から各職員の得意分野や経験を把握し、それを活かした役割分担を災害時にも適用しています。
ただし、ここで重要なのは「代替要員」の設定です。小規模事業所では、特定の職員に依存しすぎると、その職員が不在の際に対応できなくなるリスクがあります。そのため、主担当者と副担当者を設定し、副担当者も主担当者と同等の対応ができるよう日頃から情報共有と訓練を行っています。
地域資源の積極的な活用
小規模事業所が単独で災害対応を行うことには限界があります。成功している事業所では、地域の様々な資源を積極的に活用する仕組みを構築しています。
これには近隣の介護事業所との相互協力協定、地域住民との連携、自治体の災害対策との連動などが含まれます。特に効果的なのは、同じ地域にある複数の小規模事業所が協力し合う「ネットワーク型BCP」の構築です。これにより、一つの事業所では対応しきれない規模の災害にも、地域全体で対応することが可能になります。
利用者・家族との事前調整
利用者やその家族との事前調整も、小規模事業所のBCPを成功に導く重要な要素です。災害時の避難方法、家族への連絡手順、医療的配慮が必要な利用者への対応など、平時から家族と詳細に話し合い、合意を得ておくことで、緊急時のスムーズな対応が可能になります。
ある小規模グループホームでは、年2回の家族会で災害時の対応について必ず議題に上げ、家族の意向を確認し、BCPに反映させています。また、利用者一人ひとりの個別避難計画を作成し、家族の同意を得た上で、職員全員が内容を把握できるよう工夫しています。
継続的な改善サイクルの確立
成功している小規模事業所では、BCPを「作って終わり」ではなく、継続的に改善していく仕組みを確立しています。定期的な訓練の実施、職員からの意見収集、利用者・家族からのフィードバック、地域の災害リスクの変化への対応など、様々な観点からBCPを見直し、常に実効性を高める努力を続けています。
月1回の職員会議でBCPに関する議題を必ず設けている事業所や、年4回の訓練のたびに必ずBCPの改善点を検討している事業所など、それぞれの規模や特徴に応じた改善サイクルを構築しているのが特徴です。
まとめ:実効性の高いBCPを目指して
小規模事業所がBCP策定で陥りがちな落とし穴は、主にテンプレートへの過度な依存と現場実情の軽視にあります。しかし、これらの問題は適切なアプローチにより解決可能です。
重要なのは、自施設の特徴を正確に把握し、職員全員が実践できるシンプルな手順を策定し、地域資源を活用しながら継続的な改善を行うことです。形式的なBCPから脱却し、真に機能するBCPを構築することで、利用者の安全確保と継続的なサービス提供が実現できます。
BCPの策定や改善にお悩みの方は、ぜひ当研究所の無料セミナーにご参加ください。小規模事業所の特徴を活かしたBCP策定の具体的な手法について、実例を交えながら詳しく解説いたします。皆様の事業所がより安全で持続可能な運営を実現できるよう、実践的な支援を提供いたします。