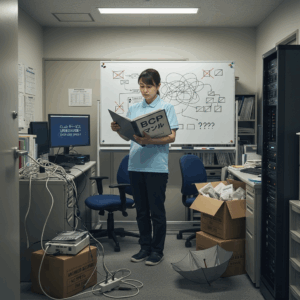厚労省ひな形の正しい使い方と注意点
介護施設・事業所において、2024年4月から業務継続計画(BCP)の策定が義務化され、多くの施設が厚生労働省の提供するひな形を活用してBCP作成に取り組まれていることと思います。しかし、「ひな形を使ってBCPを作ったものの、これで本当に大丈夫なのか?」「実際の災害時に機能するのか不安」といったお悩みを抱えていらっしゃる担当者の方も多いのではないでしょうか。
今回は、厚労省ひな形の正しい活用方法と注意すべきポイントについて、BCP初心者の方にもわかりやすく解説いたします。
厚労省ひな形の位置づけを正しく理解する
ひな形は「出発点」であって「完成品」ではない
まず重要なのは、厚労省が提供するひな形の位置づけを正しく理解することです。多くの施設担当者が誤解されているのですが、ひな形は介護施設がBCPを策定する際の「出発点」として設計されており、そのまま使用すれば完璧なBCPが完成するものではありません。
ひな形が汎用性を重視して作られているのには理由があります。全国には様々な規模、種別、立地条件の介護施設が存在するため、すべての施設に適用できる具体的な内容を盛り込むことは現実的ではありません。そのため、ひな形では基本的な枠組みと考え方を示し、具体的な内容は各施設が独自に検討することを前提としています。
例えば、ひな形の「備蓄品リスト」の項目を見ると、「食料」「飲料水」「医薬品」といった大まかなカテゴリーは記載されていますが、「何日分」「何人分」「どのような種類」といった具体的な内容は空欄になっています。これは、利用者数や立地条件、想定される災害の種類によって必要な備蓄品が大きく異なるためです。
継続的改善が前提の設計
もう一つ重要な理解すべき点は、ひな形が継続的改善を前提として設計されていることです。BCPは一度作成すれば終わりではなく、定期的な見直しと改善を続けることで実効性を保つものです。そのため、最初から完璧を目指すのではなく、まず基本的な計画を作成し、訓練や実際の災害での経験を通じて段階的に改善していくアプローチが求められます。
ひな形を自施設の実情に合わせる方法
現状把握の重要性
ひな形を効果的に活用するためには、まず自施設の現状を正確に把握することが不可欠です。この段階を軽視してしまうと、現実に即さない計画を作成してしまう危険があります。
現状把握で特に重要なのは、立地条件と想定される災害の種類を正確に把握することです。例えば、河川の近くに位置する施設であれば水害対策が最優先となりますし、山間部の施設であれば土砂災害や道路寸断への対策が重要になります。ハザードマップを詳細に確認し、自施設がどのような災害リスクに晒されているかを客観的に評価することから始めましょう。
また、建物の構造や設備の状況も重要な要素です。建物の築年数や耐震性、非常用電源の有無、給水設備の状況などは、災害時の対応方針を決める上で重要な判断材料となります。
利用者特性の詳細な分析
介護施設のBCPで最も重要なのは、利用者一人ひとりの状況に応じた対応計画を立てることです。ひな形では一般的な対応方針しか示されていないため、具体的な利用者特性を反映した計画にカスタマイズする必要があります。
例えば、医療的ケアが必要な利用者がいる場合、停電時の医療機器の電源確保や、薬剤の保管方法、医療機関への搬送手順などを具体的に計画する必要があります。認知症の利用者については、環境変化による混乱を最小限に抑えるための配慮や、徘徊防止対策などを検討する必要があります。
移動が困難な利用者については、避難時の搬送方法や必要な人員数、搬送ルートの安全確認などを詳細に計画することが重要です。これらの検討を通じて、災害時においても利用者の安全と尊厳を保持できる計画を作成することが求められます。
ひな形使用時の最も危険な落とし穴
「記載完了」を「計画完成」と勘違いする危険性
多くの施設で見られる最大の問題が、「ひな形の空欄をすべて埋めた」ことで「BCPが完成した」と考えてしまうことです。しかし、記載された内容が実際の災害時に実行可能でなければ、BCPとしての意味がありません。
例えば、職員の緊急時参集計画について考えてみましょう。ひな形では「災害発生から2時間以内に職員の70%が参集」といった目標設定の例が示されています。しかし、これをそのまま自施設の計画に記載することは危険です。なぜなら、施設の立地条件、職員の居住地域、交通アクセスの状況によって、実際の参集可能性は大きく異なるからです。
現実的な計画を立てるためには、職員一人ひとりの居住地と施設までの距離、利用可能な交通手段、家族構成(小さな子どもがいるか、要介護の家族がいるかなど)を考慮した上で、様々な災害シナリオにおける参集可能性を検討する必要があります。
職員の実情を無視した楽観的計画
災害時の職員参集について、多くの施設が楽観的すぎる想定をしてしまう傾向があります。これは、平常時の職員配置をベースに考えてしまうためです。
しかし、災害時には職員自身も被災者となる可能性があることを忘れてはいけません。職員やその家族が怪我をしたり、自宅が被災したりすれば、施設に参集することは困難になります。また、交通機関が麻痺した場合、通常であれば車で30分の距離でも、何時間もかかる可能性があります。
さらに、災害直後は誰もが家族の安否確認を最優先に考えるものです。職員に施設への参集を求める前に、まず職員とその家族の安全を確保することが重要であり、これを無視した計画は現実的ではありません。
現実的な職員参集計画を立てるためには、最悪の場合、通常の半分以下の職員数で運営を継続することを前提とした体制を検討する必要があります。そのためには、業務の優先順位を明確にし、最低限必要な業務に絞り込んだ運営体制を構築することが重要です。
実効性の高いBCPにするための具体的方法
段階的アプローチの重要性
実効性の高いBCPを作成するためには、すべてを一度に完璧にしようとせず、段階的に充実させていくアプローチが効果的です。
第一段階では、自施設で最も発生確率が高い災害に対する基本的な対応計画を作成します。例えば、地震が最大のリスクである施設なら、まず地震時の初動対応、安否確認方法、基本的な連絡体制を整備します。この段階では完璧を求めず、「とりあえず動ける計画」を作ることが重要です。
第二段階では、作成した基本計画を訓練で検証し、明らかになった課題を改善します。机上では問題なく見えた計画も、実際にやってみると様々な課題が見えてきます。連絡が取れない、備品の場所がわからない、役割分担が曖昧といった問題が必ず出てきますが、これらを一つずつ解決していくことで計画の精度が向上します。
第三段階では、他の災害種別への対応や、より詳細な対応手順、地域との連携体制などを充実させていきます。この段階になると、BCPは単なる災害対応マニュアルから、施設運営の質を向上させる総合的な業務継続システムへと発展していきます。
多職種参加による策定の効果
BCPの策定を特定の担当者だけで行うのではなく、多職種が参加することで、より実効性の高い計画を作成できます。
看護職員の参加により、利用者の医療的ケアの継続方法や、緊急時の健康状態の判断基準などについて、専門的な視点からの検討が可能になります。介護職員の参加により、実際のケア現場での課題や、利用者の個別特性に応じた対応方法について、現場目線での検討ができます。
相談員の参加により、家族や関係機関との連絡方法や、情報提供の内容・タイミングについて検討できます。栄養士や調理員の参加により、災害時の食事提供方法や、備蓄食品の管理・調理方法について具体的な計画を立てることができます。
それぞれの職種が持つ専門知識と現場経験を活かすことで、机上の空論ではない、実際に機能するBCPを作成することが可能になります。

地域連携の重要性
災害時には施設単独での対応には限界があるため、地域との連携を重視したBCP策定が重要です。
近隣の介護施設との相互応援協定は、災害時の職員不足や設備損壊に対する有効な対策となります。例えば、一方の施設が浸水被害を受けた場合に、もう一方の施設が利用者の一時受け入れを行う、職員の相互派遣を行うといった協力体制を事前に構築しておくことで、災害時の対応力を大幅に向上させることができます。
地域の医療機関との連携も重要です。災害時には救急医療体制も混乱するため、平常時から協力関係を築いておくことで、緊急時の医療対応をスムーズに行うことができます。
自治体との連携では、避難所の開設状況や道路の復旧状況などの情報収集、災害ボランティアの派遣依頼などが可能になります。これらの連携体制を平常時から構築し、定期的に連絡を取り合うことで、災害時の協力体制を実効性のあるものにすることができます。
継続的改善のシステム化
BCPは作成して終わりではなく、継続的な改善が必要です。改善のタイミングとして最も重要なのは、定期的な訓練の実施とその結果の検証です。
年に2回以上の訓練実施を通じて、BCPの実効性を確認し、明らかになった課題を改善していくサイクルを確立することが重要です。訓練では、単純な避難訓練だけでなく、情報収集・伝達訓練、職員参集訓練、代替手段での業務継続訓練など、様々な角度からBCPの検証を行います。
また、職員の入れ替わりや施設設備の変更、地域環境の変化などに応じて、BCPの内容を適時見直すことも重要です。例えば、新しい職員が入った場合は連絡網の更新、設備の更新があった場合は操作手順の見直し、周辺に新しい医療機関ができた場合は協力体制の見直しなどが必要になります。
まとめ:実効性のあるBCPを目指して
厚労省ひな形は、BCPを策定するための優れた出発点ですが、そのまま使用するだけでは実効性のあるBCPにはなりません。重要なのは、ひな形を自施設の実情に合わせてカスタマイズし、継続的な改善を通じて「生きたBCP」を作り上げることです。
現実性を重視した計画策定、利用者中心の視点、多職種参加による検討、地域連携の強化、そして継続的改善のシステム化。これらの要素を組み合わせることで、単なる書類ではない、実際の災害時に利用者の生命と安全を守ることができるBCPを構築することが可能になります。
完璧を最初から求めるのではなく、まずは基本的な計画から始め、訓練と改善を重ねながら段階的に充実させていく。この考え方こそが、実効性の高いBCP策定の鍵となります。
さらに学びを深めたい方
BCP策定でお悩みの施設担当者の皆様、ぜひ一度セミナーにご参加ください。皆様の施設の災害対応力向上に、必ずお役立ていただけるはずです。セミナーの詳細・お申込みについては、当研究所のホームページをご確認ください。